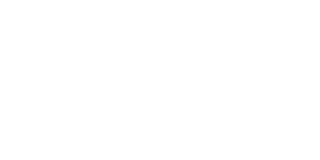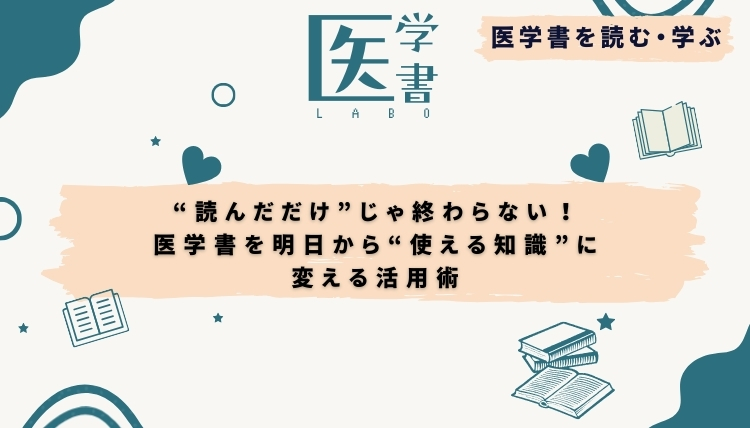◆1.今の時代だからこそ、「医学書」!
はじめましての方も、お久しぶりの方も、こんにちは。「研修医のための 魔法のロジカル診断学(じほう)」の著者、小栗太一です。
診断推論を専門とする総合内科医として、日々の臨床のかたわら、医学書の執筆や月刊誌(羊土社 レジデントノート/Gノートなど)で診断推論の連載を行っています。若手医師や医学生のみなさんに「診断推論って面白いな」と感じてもらえるような内容をお届けすることをモットーにしています。
今はスマホひとつあればガイドラインや論文をすぐに確認できる時代。でも、そんな便利な時代だからこそ、医学書をじっくり手に取って「自分の頭で考えながら読む」ことが、将来の臨床力を支える本当の土台になると感じています。
この記事では、私自身が実践してきた「明日から使える医学書活用術」を、できるだけ具体的に紹介します。研修医や若手医師のみなさんが「これならすぐに試せそう!」と思っていただけたらうれしいです。
◆2.明日から実践できる“医学書活用術”
(1) 医学書の内容をマインドマップやロジックツリーで“自分仕様”にまとめる
多くの医学書には、疾患の鑑別ポイントや思考法、診療手順などが整理されています。私の著書でも「ロジックツリー」という図を主訴ごとに紹介していますが、最初はそのまま丸写しでも構いません。ただ、ずっとコピーのままでは自分の知識になりにくいのも事実。
そこで大切なのが、自分の経験した症例を思い浮かべながら、本のやり方を自分流にアレンジしてみることです。たとえば「この患者さんはここに当てはまる?」「うちの病院のERではどこまで検査できる?」といったリアルな疑問を重ねると、文字情報が“現場で使える知恵”へと変化していきます。
また、マインドマップやロジックツリーを使って整理すると、自分の中で「思考の引き出し」が増え、実際の診療での対応がぐんと素早くなるのもメリットです。書籍の内容を自分なりに構造化し、知識と経験をリンクさせて覚えていくと、頭に深く刻まれます。メモやイラストを交えるのもおすすめですよ。
(2) ストーリーを読んだら“自分ならどう動くか”をシミュレーション
私は自分の連載や書籍の中で、ちょっとユニークなキャラクターや失敗続きの研修医のストーリーを盛り込むようにしています。具体的なストーリーがあるほうが記憶に残りやすく、自分の経験として追体験しやすいからです。
たとえば、失敗の描写を「他人事」と思って読んでいても、明日自分がERで立ちすくむかもしれません。書籍の中であらかじめ“想像上の失敗”を積み重ねることで、現場での対応力がアップします。ぜひ「もし自分ならどう対応するか」を頭の中でシミュレーションしてみてください。
(3) メモや付箋を使って言語化し、“過去の自分”と対話する
私自身、紙の本が好きで、研修医時代はお気に入りの医学書を「書き込み用・観賞用・布教用」の3冊買ったこともあるほどです。書き込み用の本には気づいたことを余白にガンガンメモしたり、付箋を貼って自分の考えを言語化していました。
あとで見返すと、「当時の自分はこんなことを考えていたのか」「今ならもっとこう考えるな」と、過去の自分との対話ができ、理解の深まりを実感できます。また、アウトプットすることも非常に大事。後輩に教える場などを活用し、自分の説明がうまくできないところを再度読み返すうちに知識が定着していきます。
◆3.結局、医学書って読むだけじゃ足りない? アウトプットも大事!
医学書を読んだだけだと、現場で「あれ? 何だっけ?」となることは珍しくありません。私自身、研修医の頃に何度も経験しました。だからこそ、「読む → 考える → アウトプットする」というプロセスは欠かせないと痛感しています。
ただ、忙しい臨床現場ではアウトプットの機会が限られているのも事実。そんなときに役立ちそうなのが「医学書LABO」です。書籍の内容に沿った問題集やSNSを通じた読者交流など、手軽にアウトプットする仕組みが用意されています。
せっかく医学書を読んだのなら、ぜひ一歩踏み出してみましょう。「読む知識」が「使える知識」に変われば、現場での診療において心強い武器になるはずです。
この記事を読んで参考になった方、面白いと思ってくださった方は
各種SNSの登録よろしくお願いいたします!
みなさまのリアクションが今後の記事を書くモチベーションになります!