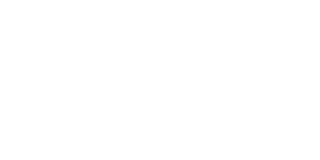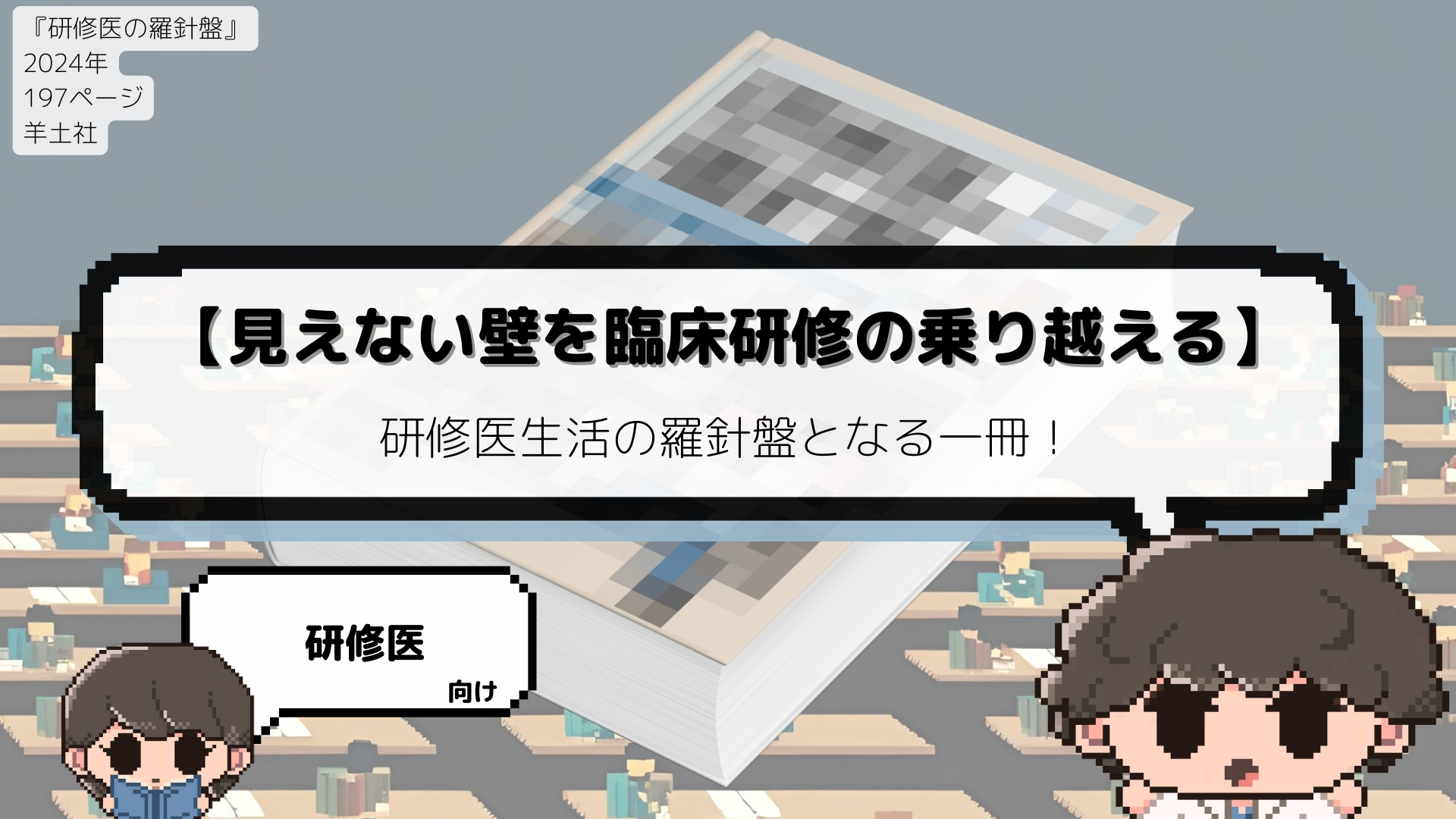お疲れさま、研修は順調かな? ちょっと表情が暗いようだけど、何かあった?
うーん、救急外来での看護師さんとの情報共有がうまくいかなくて…。向こうも忙しそうで申し訳ないし、自分もうまく説明できないし、どうコミュニケーションを取ればいいか悩んでます。
あるある。実は僕も、研修医時代は同じことで悩んだよ。看護師さんだけじゃなく、検査技師さんや薬剤師さんとの連携も大事だしね。そんな時に役立つ本があるんだよ。僕が執筆に関わった『研修医の羅針盤』、ちょっと紹介しようか。
編集長自身が関わった本ですか! ぜひ読みたいです。どんな内容なんですか?
1.本書『研修医の羅針盤』とは?
書籍名:研修医の羅針盤 「現場の壁」を乗り越える、国試に出ない必須3スキル
著者:三谷 雄己、髙場 章宏(イラスト:角野 ふち)
出版社:羊土社
発行年月日:2024年2月
メインターゲット層:医学生、初期研修医(1・2年目)
この本は僕が編集長を務め、実際に執筆・編集にも深く関わった一冊。
コミュニケーション力、臨床推論力、意思決定力という、研修医が現場でぶつかる“見えない壁”を乗り越えるための3スキルを解説しています。国家試験レベルの知識だけでは不十分な、実践的な現場対応のコツをわかりやすく詰め込んでいます。
2.この本が生まれた経緯
研修医として臨床に出たとき、病態生理やガイドラインは頭に入っていても、実際には
「看護師さんに指示を出すのが怖い」
「スタッフに相談したいのに言い出しづらい」
「どうしていつも自分は診断が遅れるの?」
といった“壁”にぶつかりがちでした。
そんな悩みを何度も経験してきた僕と、同じ問題意識を持つ仲間たちが集まって、“国試と現場のギャップ”を埋める指南書を作ろう!と立ち上がったのが本書の始まりなんです。
3.学べる内容
- コミュニケーションスキル
・看護師・コメディカルとの連携術
・不安を抱えた患者さんへの声掛け
・紹介状や電話など文書コミュニケーション など - 臨床推論スキル
・曖昧な症状にも対応できる思考回路
・ゴール思考で問題を整理する手順
・鑑別を組み立てる際のフレームワーク など - 意思決定スキル
・根拠を調べるEBMの具体的プロセス
・不確実性の中で最適な選択をするコツ
・入院or帰宅、検査or経過観察…迷った時の判断基準 など
さらに漫画パートや図表が豊富で、研修医が直面するリアルな場面をビジュアルで追体験できます。
「あ、あるある!」と共感できる症例やシチュエーションが登場するはず。
4.想定読者&活用法
「国試の知識だけでは足りない“現場力”を底上げする一冊」です。
- 医学生
臨床研修で何を学ぶべきか、その道筋を知ることで、研修前の不安が明確化します。
特に研修先で必要とされるコミュニケーション法や意思決定のヒントは、国試以降すぐに役立ちます。 - 初期研修医
1年目は「あるべき姿」をイメージしながら、壁にぶつかったら本書を開いて対策を。
2年目は、「現場でうまくいかない」具体例に対する解決策を再確認できる、心強い相棒となります。 - 専攻医・指導医
研修医の先生がなぜ躓くのか、どんな支援が必要かを理解する手がかりに。
「見えない壁」を言語化して後輩に伝えたい方にこそ、一読の価値ありです。
5.読了時間の目安とポイント
ページ数:約280~300ページ(予想)
推定読了期間:6~8時間程度
イラスト・漫画が多いので文章量自体はそこまで多くありません。
平日のスキマ時間に少しずつ読み進めたり、週末に一気に読破するのもOK。
臨床現場で疑問にぶつかったタイミングで、「どう考えればいい?」とピンポイントに見返す使い方もおすすめです。
6.まとめ
僕自身の研修医時代の悩みや葛藤が詰まった、そしてその解決策をまとめたのが『研修医の羅針盤』です。
コミュニケーション・臨床推論・意思決定の3スキルは、国試の勉強だけでは身に付きません。
でも、この3つがあるかないかで研修生活の充実度がガラリと変わるのも事実。
もし「看護師さんとどう話していいか分からない」「曖昧な症例で診断が遅れる」など困っているなら、まずはこの本を読んでみてください。
きっと明日からの診療が、少しだけスムーズになるはずです。
『研修医の羅針盤』が、あなたの研修航海の道しるべになれば幸いです。
この記事を読んで参考になった方、面白いと思ってくださった方は
各種SNSの登録よろしくお願いいたします!
みなさまのリアクションが今後の記事を書くモチベーションになります!