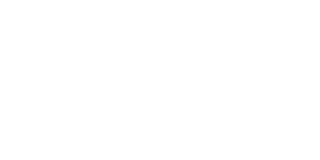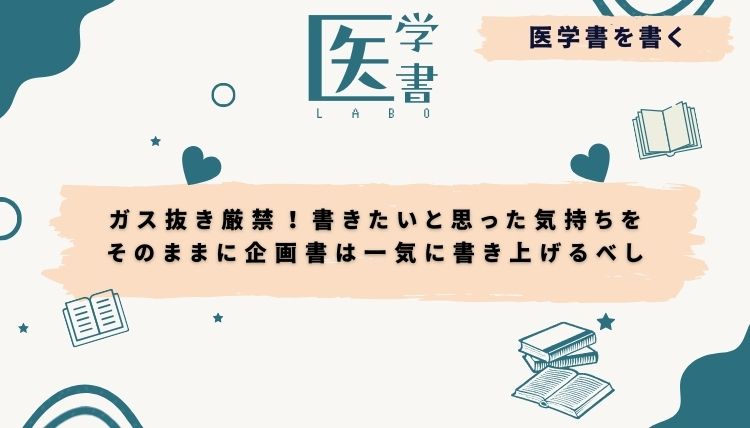医学書の企画書を書く――それは「自分の制作意欲という内圧を限界まで高める」行為にほかなりません。
私はいつも「書き上げるまで絶対に人に話さない」ことを自分に課しています。
企画は風船や圧力鍋のように内側からエネルギーを蓄えるほど濃度が増し、言語化した瞬間に“ガス抜き”が始まってしまうからです。
1. 内圧とは何か?
企画の内圧とは「自分だけが知っているワクワク」を圧縮する力。
医学書の場合、「なぜこのテーマを今、書かねばならないか」という使命感や、「読者にどんな変化をもたらすか」というビジョンを高温高圧で煮詰めるプロセスです。
2. 相談は“書き上げてから”
「途中経過を共有してフィードバックを…」と考える気持ちはわかりますが、書き上げ前の多数意見は企画の尖りを削り、平凡にしてしまう危険大。
まずは自分ひとりで熱量を一気に文字へ落とし込む。
完成稿(たとえ粗削りでも)を持ってから人に相談すれば、軸を失わず建設的な議論ができます。
私が運営し、みんなで医学書の制作をしているオンラインコミュニティ『医学書クリエイティブLABO』でも同様にお伝えしています。
3. SNSガス抜きを防ぐルール
- 進捗ツイート禁止:「◯章書けた!」は快感と引き換えに内圧を放出
- ネタバレ禁止:キーメッセージを公開すると驚きが半減
- アウトライン非公開:章立ては“爆発”の瞬間まで秘匿
“いいね”はドーパミンをくれますが、同時に企画の温度を下げる麻薬でもあります。
これは私も陥りがちな失敗ばかり。反面教師にしたいですね。
SNSは出版後の広報ツールと割り切るくらいの覚悟が合ってもいいのかもしれませんね。私はそこまで心が強くはないのですが…。
4. 内圧を高める実践ステップ
まずは、企画のテーマを「ひとこと」で表現してみてください。
たとえば「救急初動の“つまずき”をゼロにする本」のように、読者へ届けたい核心を短いフレーズに落とし込むと、書くたびに軸がぶれず、内圧がじわじわ高まります。
次に、自分だけの締切を決めましょう。
1週間で粗原稿を書き上げ、さらに1週間で図表のラフを作る
といった小さな区切りを設定すると、日々の執筆に心地よい緊張感が生まれます。
カレンダーに書き込んで、進捗が見えるようにするのもおすすめです。
そして、毎日少しの時間を使って「読者がページをめくる瞬間の表情」を想像してみてください。
読み手が喜んでくれる顔――思い浮かべるだけで、原稿に込めるエネルギーが自然と増していきます。
特にブログ記事などに有効な手立てです。
読者の喜ぶ姿を思い描くことは、内圧を保ち続ける大切な燃料です。
最後に、原稿がひととおり形になったら、1日ほど寝かせてみましょう。
少し距離を置いてから読み返すと、熱が冷めても伝わる力強さが残っているか客観的に確認できます。
丁寧に補強し、再び煮詰めてあげてください。
この4つのステップを意識しながら進めていくと、企画書に込めた熱量がしっかりと守られ、読者の心に届く一冊へと育っていきます。
まとめ
医学書の企画書は「自分の熱量を圧縮 → 一気に爆発させる」からこそ読者の心を打ちます。
途中でガス抜きせず、まずは誰にも見せない“圧力鍋”モードで書き切ってみてください。
そのあとでこそ、他者の視点が磨き上げの砥石になります。
さあ、あなたの内圧――この記事を読んで、もう十分に高まっていますか?
医学書執筆の夢を現実に変えたいあなたへ。Discordで相談し、オンライン勉強会で切磋琢磨。企画書添削から出版社アプローチまで仲間と伴走します。
「医学書クリエイティブLABO」に参加しませんか?
ゼロから学べる『初めての医学書の書き方』というnote記事を公開しました。
テーマ設定、構成術、進捗管理、著者契約まで余すことなく解説。
まずはこの記事で基礎を固め、あなたの一冊への第一歩を踏み出しましょう!
この記事を読んで参考になった方、面白いと思ってくださった方は
各種SNSの登録よろしくお願いいたします!
みなさまのリアクションが今後の記事を書くモチベーションになります!